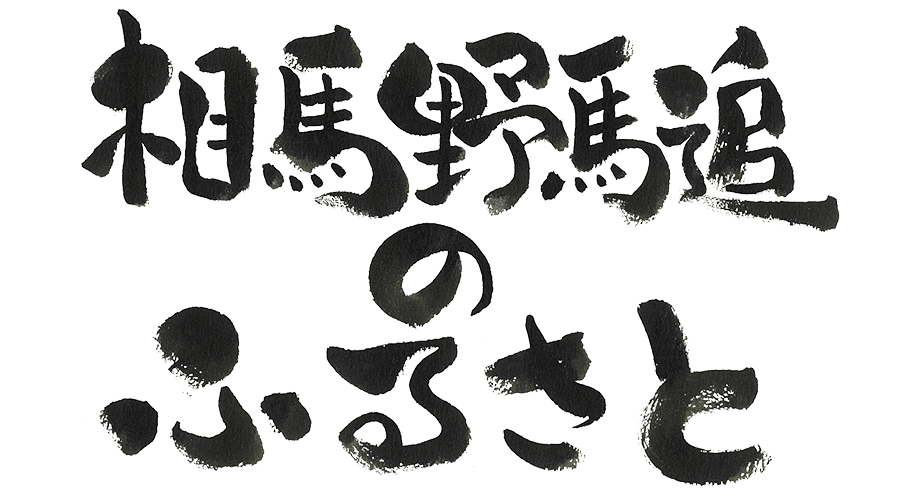馬を追う野馬懸(のまかけ)、甲冑(かっちゅう)競馬、神旗(しんき)争奪戦、お行列など、旧相馬中村藩地域(福島県南相馬市、相馬市)で繰り広げられる相馬野馬追は東北六大まつりのひとつに数えられています。
この相馬の野馬追はいつ、どこで始まったのでしょうか。
時は平安時代、京都の朝廷に反旗を翻し(ひるがえし)、自ら新皇を名乗って東国の独立を図った平将門公は騎馬戦を得意としていました。
将門公は下総国(しもうさのくに)小金ヶ原(千葉県北西部)で、放たれた野馬を敵兵に見立てた軍事訓練を行っていたのです。
これが相馬野馬追の起源です。

以来、相馬野馬追は平将門公を遠祖とする相馬氏に伝わり奥州相馬氏の祖となる相馬重胤(そうましげたね)が下総国相馬郡増尾村から陸奥国行方郡(むつのくになめかたぐん)へ下向するに伴って、相馬野馬追も現在の福島県相馬地方に伝えられました。
また、葛飾郡流山郷からは鳳輦(ほうれん)に奉って(たてまつって)きた妙見(みょうけん)・塩竃(しおがま)・鷲宮(わしのみや)の三神を行方郡大田村(南相馬市原町区中太田)に勧進(かんじん)しました。
こうして陸奥国に移った相馬氏から江戸時代の相馬中村藩を経て現在まで連綿(れんめん)と続けられ、1952年に国指定重要無形民俗文化財に指定されました。
相馬野馬追のふるさとは、下総国相馬郡増尾村(現在の柏市増尾)なのです。

 見る
見る 遊ぶ
遊ぶ 買う
買う 泊まる
泊まる 柏の昔話
柏の昔話