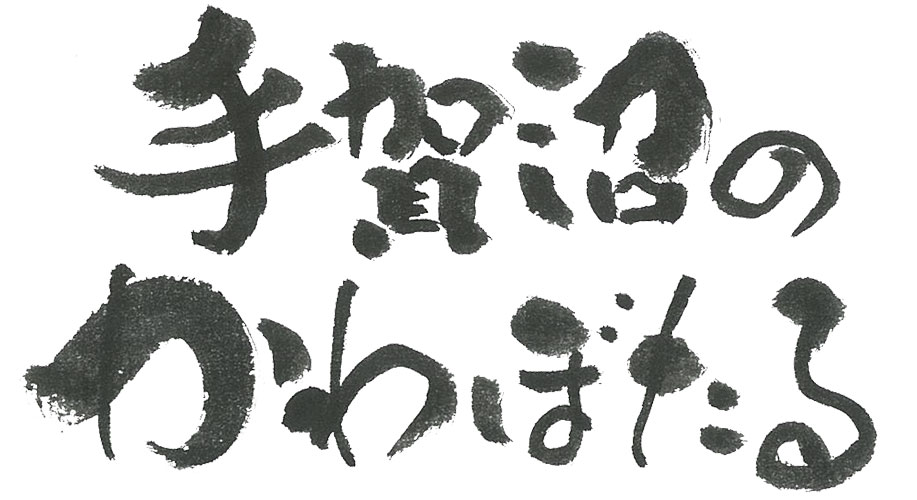むかしむかし、手賀沼が今よりもずっとずっと大きかった頃のお話しです。
手賀沼は川のように長かったため、沼と書いて「かわ」と呼び、沼向こうは「かわむこう」、沼仕事は「かわしごと」、沼越えは「かわごえ」と呼んでいました。
これは手賀沼によく出た「かわぼたる」と呼ばれた蛍のような青白い光の怖い怖いお話しです。

ある年の8月14日、手賀村の若者、孫六と弥平が手賀沼を見渡せる高台で話しています。
「なぁ弥平よ。今日は波も静かだから夕涼みもかねて日秀(ひびり)の盆踊りに行かねぇか」
「いやいや、お盆の日はかわごえはするなって婆さまが言ってたぞ、なんでもかわぼたるが出るってよ」
「なんだ、いしゃあかわぼたるが怖えのか?ほたるなんかなんでもねぇべ」
「いや怖くはねぇけどよ。まぁ早めに帰ってくりゃあ、大丈夫か」
「んだんだ、なら舟さ出すべ」
ふたりは、2隻の農舟に分かれて日秀村(現在の我孫子市日秀 の盆踊りへ行きました。

どれだけ時間が経ったでしょう。楽しく踊り終わって、いよいよ手賀村へ戻ることになりました。
船着き場から、孫六は枯竹竿、弥平は真新しい青竹竿を操って農舟をこぎだし、沼(かわ)中まで来たときのことです。それまで あんなにきれいな月が水面を照らしていたのに、急に真っ黒な雲が空を覆い、雨が降り始めました。
すると先に行く孫六の船竿の先端に青白く強い光の火の玉がとりつきました。
孫六はそれを一生懸命とり払おうと、必死で竿を舟にたたきつけたのです。
その音を聞いた弥平が見ると火の玉は砕けて水面で光り、なおも新しい火の玉と孫六がたたかっています。
そのうち、弥平の竿先にも火の玉がつきました。
竿先を水面で何度もたたき、運よく火の玉が消えたので弥平は必死の思いで 舟を手賀のかわばたにつけて一目散に家へ帰り、布団の中に潜り込んでしまいました。
次の日の朝、弥平の家の戸をどんどんと叩く音で目が覚めました。
戸を開けるとそこには孫六の両親が立っていました。
「うちのせがれはどうした?知らねぇか?」孫六が家に帰っていないことを知った弥平は昨夜のことを話しました。
それは大変だと、皆で沼へ行ってみるとあわれにも孫六は舟の近くで亡くなっていました。
いそいで孫六を引き上げたところ、頭には火傷のあとがあり、先端が焼けこげた舟竿が舟の中に投げ捨てられていました。
お盆の夜に、かわしごと、かわごえをするとかわぼたるに襲われる、手賀沼にはこんな怖いお話しもあったのです。

 見る
見る 遊ぶ
遊ぶ 買う
買う 泊まる
泊まる 柏の昔話
柏の昔話