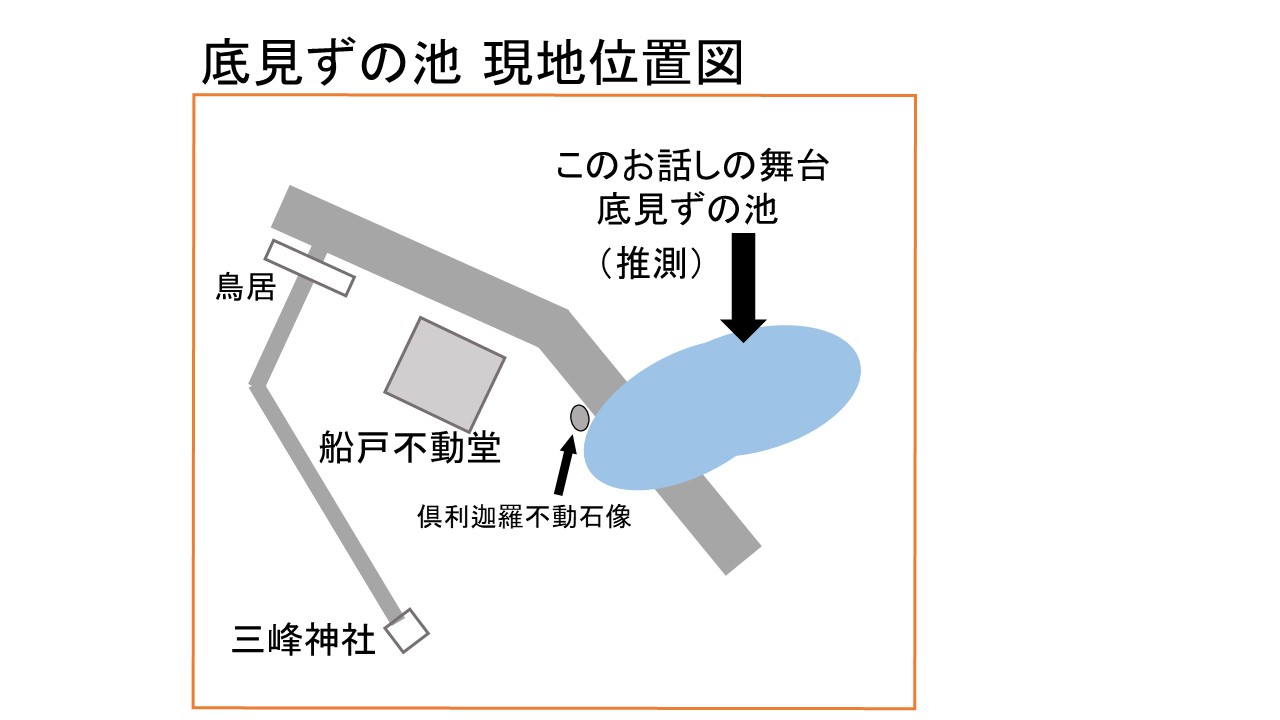ここは船戸代官所にほど近い、うっそうと木々が生い茂って、昼でもうす暗い不動明王の森。南側下には、水がれを知らないように満々と水をたたえた池があります。村の人たちはこの池を底見ずの池と呼んでいます。
それは昔、ある夜おそくのことです。二人の村人が、しーんと静まり返ったこのあたりを通りかかりました。自分たちの足音にもびくつきながら、ろくに話もしないで、足早に通り抜けようとしたときです。ぴしゃっぴしゃっというかすかな水音に、ぎょっとして立ち止まってしまいました。
「おい、何か音しなかったか。」
「うん、したした。池の方からだな。なんだんべ。」
二人が池を見ますと、何やらぽうっと光っているのが見えます。
「気味悪いな。急いでけえんべ。」
「いや、もうちいっとそばまで行って見ねえか。」
こわさ半分、見たさ半分の二人はぴったりくっついて、おっかなびっくり池の方に近づいて行きました。
と、どうでしょう。金色のうろこをかがやかせた、大蛇がたわむれているではありませんか。池の水も七色に変わりきらめいています。
「おい、見たか。ゆめじゃあんめえな。」
「ああ、見た。すげえものを見たもんだ。」

この話はすぐ村の人たちのひょうばんになりました。あの大蛇はどこからやって来たのでしょうか。なんでも、印旛沼の主がこの池の主を見そめて、毎ばん通ってきたのだという話ですが、どこをどう通ってきたのかはよくわかりません。
満々とたたえられた水も今はなく、道路わきに、龍がまきついた姿を刻んだ石が立てられています。明治のころには、目や、うろこに金ぱくがぬられていて、かっと目を見開いた龍の姿が水にうつり、子ども心にもこわくて、外に出られなかったとお年寄りが話しておりました。

 見る
見る 遊ぶ
遊ぶ 買う
買う 泊まる
泊まる 柏の昔話
柏の昔話